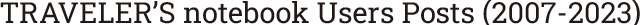ゴミ巡回 その1
「運転手さん、用賀で降りてくれますか?。ちと、用足し思い出したんで」
大南は思い付いた瞬間、大きい声でそう頼んだ。それから、我ながら名案だと思った。
「用賀からどちらに向かいます?」
「とりあえず成城の駅まで出てください」
車は夜中の首都高を風のように進んでいく。チラリと時計を見ると2時を回っている。さすが、首都高の眼下に広がる世の中も就寝中と見えて、窓に広がる景色は艶消しの青黒色。ミッドナイトブルーというのだろう。そして、世の中の上空を移動中の車は、2軒回った後カラオケで咽を痛めた大南と勤労に励む運転手さんなのだ。
最後に牧田課長と2回ガナッた「遠くで汽笛を聞きながら」がいけなかった。
『なにもいいことが、なかったこの街で・・・』というフレーズ。つい、気持ちが入ってしまうのか二人とも吠えるような歌い方になってしまう。
滑るように車は首都高のスロープから環八に着地して、一路、大南の思い付きの場所へと向かうのだ。
「お客さん、では、とりあえず成城学園の駅へまいりますね。それから平塚でよろしいですか?」
なんといい気分だろう。大南のポケットにはタクシー券、運転手君も「平塚」という言葉も効いてニコニコ、物腰も柔らかで心なしか運転まで軽やか。まるでサンダーバードに出て来るパーカーとお嬢様のようだ。
いつのまにか車も6輪タイヤのロールスロイス。
「他にどちらかお寄りしますか、お嬢様?」
「とにかく成城よ。またその時言うわ、運転お上手よパーカー」
「ありがとうございます、お嬢様」
やがて車は世田谷通りに入り、一段と道幅も狭くなったが、パーカーの腕もいいのか順調な走行を続けている。
清掃工場の煙突。NHK技研。右側にスズキのディーラー、左側に中古バイク屋・・・。
「運転手さん、これ大蔵病院?」
左側に見え出したホテルを指して大南が尋ねた。
「ええ、大蔵病院です」
「へーっ、すっかり変わっちゃってホテルみたいですね」
大南は新入社員当時、10年近く、このあたりで生息していたのだ。50ccのバイクと中古の軽四駆で走り回った道だが、運転される後部座席からながめるせいか、流れが少し速すぎるようだ。
記憶のコマ送りが追いつく間もなく
「お客さん、駅前の通りに出ましたが?」
パーカーが呼んでいる。
「ちょっと待ってください。こりゃ、裏駅か、表駅側か・・・」
「お客さん、確かこのあたりの踏切はもうなくなって、どうですかね? 裏側なんですかね・・・?」
どうやら電車の線路は地下にもぐってしまい、見渡す風景から電車の姿がなくなった。
そこにあって当たり前と思っていたものがなくなると頼りないものなのだ。
どこかの地方都市でもそうだった。新幹線の駅ができてもとの古い駅舎が消え、線路も高架に変わってしまうと、どこの駅前も区別がなくなって、はるばる訪ねた距離感すらなくなってしまうから不思議だ。おまけに新幹線は「文化」も運び込むのか、青っぱなの小僧もリンゴ娘もモンペ姿のバアさまも、ご当地なまりも一掃されてしまうから面白い。
成城駅前から電車が消えた?。踏切の遮断機の音もしない。当たり前とあきらめていた踏切渋滞もない。かすかな記憶に残る日石のガソリンスタンドを頼りに平面をゆっくり回転させてみる。
「待って、いま芯をあわせてっから・・・。おやっ? 運転手さん、あのスタンドのところを左に入ってもらって・・・」
車は一本道路をまたいでスタンドに向かう。今、なんとなくまたいだ道、あれが以前の線路ということらしい。
「そしたら、まっすぐ突き当りまで行ってもらうと、坂道があるんで下ってください」
ここ成城は資本主義の街。
サラリーマン一代で30年、35年ローンを組んで戸建てを買おうと思ってみても、少し計算しただけで不可能と知れる。何か数式がおかしいのか、月々を少し上げ、思い切ってボーナス払いを倍掛けに引き上げてみても、さらに郊外の戸建てが買えるほどの余りが出てしまう。ちなみに生涯稼ぐであろう給与を全額投入してみたとき、はたっ、と限界に気付く。
ではとローン期間を60年、70年と延ばして投入したとき、思ってもみない事象が現れる。やはり償却できないわけは単純だ。利子が嵩むだけで期間を伸ばした効果に薄い、「ローン限界」に陥りかねない。全支払い額が生涯生産金額を大幅に上回ってしまい、公式を内輪にとどめるには、幼児もできるだけ早い時期にローンをはじめ、勤めにも出て、一日一食、三日で二食、病気もせず、毎日元気に80以上まで返済し続けるうち、ある日、墓に入る直前、我が家になる可能性がいくらかあるくらいなのだ。ということはこの街に一代サラリーマンの家はなく、親の七光りを引き継いだ代々のすねかじり。ひょんなことからオーディションに受かってしまった芸能人。あとは宝くじ成金と身寄りのない老人宅に、秒読みに入ってから突然現れた遠い親戚くらいしかいないのだ。
当時、不動産屋の売り出し物件を見かけた大南の考えは今もって変わっていないばかりか、運のいい人間も、その運が定期的に当たり続けないと、ご近所付き合いやら子供もそれなりの私学へ通わせたりが続かず、住んでいることにならない。そして、思い出すのが何を買っても、何を食べても高いこの街で、何十年と生息し続ける必要経費を考えただけでも、今もって大南の年収では足が出てしまうほど、底無しの資本主義に染まったエリアなのだ。
目には見えないが、こうやって通過している間にも、水漏れ、ガス漏れのように『¥』が闇の夜空へ拡散しているのを感じるのだ。
何軒か見覚えのある芸能人宅も通り過ぎたが、近年とんとTVにも出てないあいつはどんな気持ちで暮らしているのかわかったものじゃない。
やがて道路は大南の記憶どおり突き当たり、左に折れると急坂にさしかかる。半端な下り坂じゃない。20メートル分くらいの落差はあるだろう。
思い出すのは大雪の朝、革靴で登るには道端の潅木につかまらなければならなかったこと。当然、その日の帰り道、坂の上からながめるスロープは、どこかのスキー場の中級コースによく似ていた。しかし、少し違うのは、これから滑り出す楽しい予感はみじんもなく、資本主義の平面からくだっていく、否、落ちていく、1メートルあたり地価が一桁ずつ下がっていくような暗い坂道なのだった。
車は坂の底でかろうじて右にハンドルを切った。
すると岩棚のように、思ってもみない広い平面がひらけるのだ。
大南は秘境のように突然現れるこの広がりが好きだった。なんとなくネクタイをはずしたような、ほっとする平面なのだ。
「運転手さん、そこの空き地に首突っ込んで止めてください。すぐ戻りますから」
大南は両足をそろえ、車の脇に立ってみた。
かれこれ20年ぶりに踏みしめる地面。
帰ってきたというよりは、まるで放火魔が忘れていた現場に、ひょんなことから戻ってきたような胸騒ぎの平面。そこに6畳一間の三軒長屋だった。トイレはまだ汲み取り、風呂もなく、夏場は銭湯に行くのも面倒で、コンクリーのたたきで闇夜にまぎれてホースの水浴びで済ませていた生活だった。
大南はしばらく周囲をながめて歩き出した。