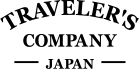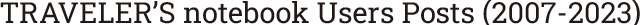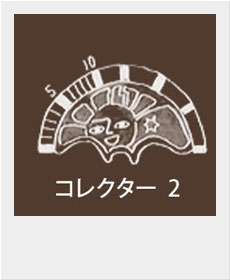
コレクター 2
やがて若主人は彼にロンジンを譲ることに了解しました。その理由について彼は決して話してくれません。
「いや、そんな大した裏話があるわけじゃないさ。ほとんどの人はこんなボロ時計のどこがいいって思うだろうが、とにかく好きなんだ」
そんな風に言ってニヤリとするだけなのです。
しかし、実際自分の物として手にして、彼は半年以上も使う気にはなれなかったのです。
「あまりに古すぎる…」
彼にはその重圧感を跳ね返すだけの明るさがありませんでした。薄汚れた文字盤、無数にひび割れの入ったガラス、一見ガラクタ同然の中で40年前と同じ時間を正確に刻んでいるのです。それは少し無理をすれば、すぐ壊れてしまうかすかな正確さです。そして、半年ほどして使い始めてトラブルが続きます。
ゼンマイが切れました。
手巻きの時計の一番の悩みがこれです。そもそも手巻きの時計に精度を要求してはいけません。いけないそうです。手巻き時計の世界では、少し進む時計以外時計ではないそうです。むろん、遅れる物はもはや時計とは呼びません。一日に30秒~1分進む物こそ正確と呼ばれるそうです。その進み具合をつかみ、今度は使用者側が体で合わせるのです。
ゼンマイを100%巻き上げ、戻りきるまでの動きを覚えます。当然、戻り初めは元気一杯、時間は進む傾向に「強」です。逆にゼンマイの最後は、時間は遅れる傾向にあります。この遅進の推移を体で覚え、巻き回数と巻く時間帯を組み合わせることにより正確さをコントロールするのです。
なるほどこれは一理あります。
遅進の関係はグラフを思い浮かべればすぐイメージできます。
正確な時間の流れを水平線としますと、手巻き時計のそれは左肩上がりから右下へ斜めに下る線として表れます。ゼンマイの戻り初めは時間より早めに、ゼンマイの最後は時間より遅く、左から右へ下る斜めの直線です。そして、下りきる頃『巻き』が入って一気に左上まで上昇します。だからちょうど「N」の字の連続したパルス波形のように表れるはずです。あとはこの「N」の字が時間の水平線の上部・下部で同じ高さになる条件を探るわけです。「N」の字が水平線よりも上側にずれる場合は、ゼンマイの最後の部分から一日分の巻き回数を選びます。逆に下側にずれる場合は、ゼンマイの戻り初めの元気な部分を中心に一日分の巻き回数で芯に合わせるわけです。下降線のどの部分をピックアップするか、簡単なようで複雑な理屈です。
実際ゼンマイを切ってみて彼は深く反省するのです。改めて勉強したのはゼンマイのもうひとつの理屈です。ゼンマイはフルに巻き上げてしまうと寿命に短いのです。しかも数多くの歯車、シャフト、軸受けに対して、必要限度以上の力を与え続けることになるのです。
ゼンマイはその巻き数を数えるところから始めます。100%巻き上げて戻り切るまでの持ち時間を計ります。普通48時間ほど、ものによっては72時間、3日近く動くタイプもあるそうです。そのちょうど半分近くを目標に一日分動くリューズの巻き回数をつかみます。
巻き回数が1日分よりも少しでも多いと、10日ほどでゼンマイはフル巻きとなるでしょう。逆に巻き回数が少ないときはやがて時計は自然と止まってみせるでしょう。その時計に合わせ、ゼンマイのキャパシティ半分ほどの巻き回数を中心にした一日分を徐々に探っていきます。その答えは一番遅進の誤差も少なく、ゼンマイにも無理をさせない理想的な一日分として顕れるでしょう。このロンジンでは18回ほどの巻き回数になるそうです。
気の長い作業です。
そして、ゼンマイを一日一度巻くものと定めます。それはなんとなれば2日に一度や日に何度も巻くのでは習慣化するのは不可能に近いからに他なりません。その時間帯と巻き回数を体得し、それらを日常生活の中に自然と潜らせてしまう。しかもこれらすべては無意識でなくてはいけません。
手巻き時計はまだ機械に人が歩み寄る時代のツール。何年も巻かれ、戻されたハガネのゼンマイはいつかは切れる理屈です。その前提に立って、いかに長持ちさせるかを模索する。
「これらをマスターしてこそ、初めて時計をツールとして使いこなしたことになる」
そういう時代のアイテムだというのです。
さて、ゼンマイ修理から戻ってしばらく、今度は『天ぷ』と呼ばれる歯車の軸が折れてしまいます。彼は不用意にも自宅でテーブルの上からフローリングの床へ落としてしまったのです。
その高さ70センチ。40年以上も働き続けてきたロンジンにとって、それはビルのワンフロアー分の高さ、コンクリートの叩きほどの堅さに匹敵したのでしょう。すっかり磨き込まれ、ほっそりとした歯車の軸はこけし型の爪楊枝のくびれのようにところどころかすかな部分を持っていて、いきなり受けた衝撃の振動を緩衝しきれず一気に腰砕けたのです。無理もありません。なにしろこの天ぷと呼ばれる部品は常に右に左に回転していて、休むということがありません。
「1秒間に左右半回転づつ、まさに時計の心臓」
だそうです。
ゼンマイの力をため込んだままロンジンはふたたび修理に出されるしかなかったそうです。
さて、先ほどから何度か言われてきましたように、40年から昔の同一部品など、もう探しているだけで膨大な時間を要すことでしょう。同じような太さの、否、この場合細さと呼ぶべきでしょう、金属棒から削って新たに作る方がまだ現実的だったようです。4ヶ月近くの日数の中でようやく復刻されたのです。
忘れかけた頃、突然の留守電話の声に驚きながら、彼は翌日すぐ受け取りに行ったそうです。今、私達が座るこのカウンターです。
「ずいぶん長いことお待たせしました。私どももなんとかお直ししようといろんな職人に当たっていました。でも、大丈夫。ようやくあがってきました。どうぞ大切にしてください」
「ええ、もちろん大切にします」…
そんな受け答えの後、さっそくロンジンを腕に、彼は駅のプラットホームに立ちます。見上げると、今立ち寄ったデパートが正面に建っています。そして、この4ヶ月を想い左腕を持ち上げます。ところがもうロンジンは止まっているのです。彼はそのままデパートに戻ります。
左腕がいやがる体を引っ張っていくような気分だったといいます。
次は自宅の駅に降り立つまで動いていたそうです。また、その次は翌日までと徐々に記録を伸ばしているようにも見えたそうです。
しかし、何度目かに持ち込んだ際
「そもそも修理というのは、直って戻ってくることなんじゃないですか?。…私も言いたくありませんが」
思わず,彼はそう言ったそうです。
それから2ヶ月後、彼の前に現れた白衣の店員は自信にあふれた顔で講釈したそうです。
「大変でした。もうこれ以上ご迷惑はかけられないと思い、探しました。腕のいい職人です。ご覧ください、最近の時計の本にも載っています。…
この先生です。ようやく都合付けてもらって、昨日直って来ました。…
もう止まることはありません。機械はまだまだ元気ですから」…
なんでも、本場スイスに留学し、国内では機械式時計の第一人者。「匠の技」を持つ職人と呼ばれる人物だそうです。
それから3年近く、彼のロンジンはなるほど白衣の店員の話のとおり、順調に働き続けて来ていたのです。