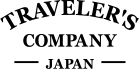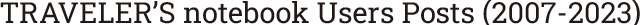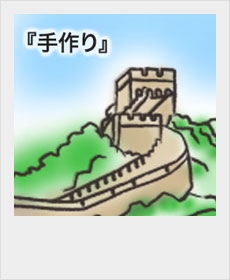
『手作り』
ある金曜日の夜会社帰りに行き付けのパブに寄った。 「みんなのトラベラーズノート」や「みんなのトラベラーズフォト」でお馴染みのtomo-sさんと邂逅した。 僕の書いたストーリを読んで僕に会いたいと思っていただいていたらしい。
飯島氏の日記を読んで出掛けて行ったそのお店が僕の行きつけだと知り、何度も足を運んでいらしたことを店のオーナーから聞いていた。その日偶然出会えたtomo-sさんはとても気持ちの良い方で、初対面とは思えないほど短時間で意気投合した。「次回作は『手作り』というタイトルで書いています。」と話すと、常に持ち歩いていらっしゃる彼こだわりの手作り品をいくつか見せていただいた。愛しそうに鞄から取り出す様子にそれぞれのものに対する愛情が垣間見えた。
北京オリンピックの余韻がまだ残っている。野球は残念だったが、日本にとどめを刺したジャイアンツのイ・スンヨプのホームランには感動した。感動したのはホームランそのものではなく、あのホームランで勝利して14人の若い選手が徴兵を免れたことだ。今シーズンの彼のジャイアンツでの活躍を考えるとファンは堪らないと思うが、彼の一打で14人の若者が、例え義務であれ、武器を手にしなくて済んだことで彼が「反韓」を買うことはないと信じたい。
初めて僕が北京を訪れたのは1996年だった。当時勤めていた会社の北京でのプロジェクトのためだった。何度か足を運び、プロジェクト本番に備えて出国する前に、プロジェクト終了後に現地で2日間有給休暇が欲しい旨を上司に伝えた。アメリカ人女性の上司は僕が母を呼び寄せてその2日間を過ごすなら許可すると言った。もちろんそのつもりだった。上司のその一言は前年に夫(僕の父)を亡くした母を慮ってのことだと思った。
その後彼女の傘下を離れるまでこのような心遣いをたくさんいただいた。彼女には今でも大感謝している。
どこでどう伝わったのか取引先が僕の計画を知っていた。プロジェクトが終盤に差し掛かったある日、我々の控え室に宛がわれていた立派な応接室に資料を取りに戻ると、取引先の社長(女性。中国共産党女性部のナンバー2の方だったらしい)が、他のスタッフ達とともにそこにいた。僕の顔を見ると「お母様がいらっしゃって万里の長城へ行くんですって? 車とガイドを用意したからお使いなさい」と笑顔で言ってくれた。現在は分からないが、当時中国では地位が高い人は例え英語が話せても絶対に通訳を介していた。いきなり彼女が英語でそう言ってくれたときは驚いた。日本人らしく最初は遠慮して見せたがありがたくご厚意に甘えさせていただいた。
プロジェクトが成功に終わった翌日、一緒に来ていた同僚の一人も加わり万里の長城へ出掛けた。北京の中心からかなり長い間車に乗っていた。ご厚意の有難さが早くも身に染みた。風が強かったが5月の万里の長城は暑くもなく寒くもなく快適だった。観光客も少なかった。後年再訪した母はこのときほど気候に恵まれゆったりとは歩けなかったと言っていた。学生の頃日本史や世界史で習ったところはいくつも訪れたが万里の長城ほど感動したところはなかった。これは今も変わらない。アップダウンがあり、眼前に果てしなく続いている長城を歩きながら「これって手作りなんだ」と思った。
そう思った途端に一歩一歩噛み締めながら歩を進めた。景色の雄大さはもちろんだが、手作りという点に心を奪われていた。当時どんな技術があったかは分からないが凄いものを手で作ったものだ。
ガイドとして付いてくれたのは取引先の営業の女性だった。まだ学校を出たばかりだったらしいがしっかりした英語を話していた。説明はもちろんのこといろいろと尽力してくれて有難かった。帰りの車中でいろいろな話をした時に、彼女が今一番したいことは海外旅行で欲しいものはウォークマンだと言った。学校も卒業し海外企業との合弁会社で働き外国語もできるのだからそれなりに収入もあるのだろうと思っていたから意外だった。ホテルに到着すると同僚が急にガイドをしてくれた彼女にちょっと待つように言った。同僚は自室に戻り自分のウォークマンを持って戻り彼女にそれをあげた。彼女が狂喜したのを今でも覚えている。
現地の富裕層や外国人向けのショッピングセンター前の交差点には物乞いをしている幼い子達がたくさんいた。一方でガイドをしてくれた立派な職業についている彼女のような人達もいる。今しきりに言われている格差というのはこういうことなのかと改めて思う。
その後北京には何度か訪れたが、もう7, 8年行っていない。オリンピックを開催したくらいだからかなりの西洋化が進んだことだろう。格差もかなりのものだと伝え聞く。
我々が普段に何気なく利用しているファストフードのお店も相変わらず富裕層しか利用できないのだろうか。最新の携帯音楽機器はどのくらいの年齢層に普及しているのだろうか。
万里の長城に限らず彼らの作ってきたものは世界にその手先の器用さを知らしめている。
日本も職人の数が激減していて後継者が不足している。職人が作る手作りのものはお金持ちの贅沢品になっている傾向は非常に残念である。手作りという点で中国と技術交流し友好的に国交が発展できないものかと強く思う。