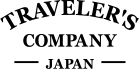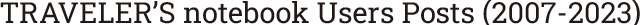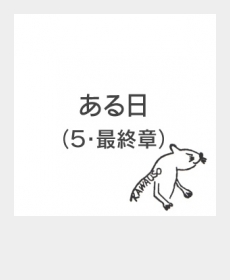
ある日(5・最終章)
それから2年後、3人はそれぞれこんな注意書きを目にすることとなる。
CD(コンパクトディスク)の取扱い方
(1)ディスクの持ち方
なるべく信号面(虹色に光っている側)に
触れないよう、エッジを持つようにしてく
ださい。
(2)ディスクの保管は必ずケースに入れ、
高温多湿の場所や直射日光の当たるところ
極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管
して下さい。
(3)ディスクに付いている注意書きは必ず
お読みください。
(4)ディスクのお手入れ
ディスクに指紋やホコリが付いた場合、汚
れにより音が飛んだり音質が低下すること
があります。ディスクの汚れを拭くときは、
柔らかい布で円周に沿って拭かず、内周か
ら外周へ軽く拭きます。ディスクの清掃に
は別売りのディスククリーニングセット
(JV-D11)の使用をお勧めします。汚れ
がひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、
よく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾
いた布で水気を拭き取ってください。
(5)レーベル面に紙やシールなどを貼り付
けたり、傷などを付けないようにして下さ
い。ノリなどがはみ出した場合、ディスク
が取り出せなくなるなど故障の原因になり
ます。特にレンタルディスクにおいてはラ
ベルが貼ってある場合が多く、このような
故障が起こる恐れがありますので、のりな
どのはみ出しを確認してからご使用下さい。
損傷のあるディスク(ひびやそりのあるデ
ィスク)は使用しないで下さい。ベンジン、
シンナーなどの揮発性の薬品は使用しない
で下さい。また、レコードスプレー・帯電
防止剤などは使用できません。
このシステムは日本国内のみ使用可能です。
また、海外のディスクは解読トレーススピ
ードの違いにより、再生できない場合があ
ります。
野口は出向先の音響製品問屋の倉庫。何気なく手にした、返品で戻ったダンボールからのぞいていたCDプレーヤーの取扱説明書。
微は駅前にOPENした貸しレコード屋のCDコーナー。そろそろCDへの乗り換えを考えはじめた矢先、何気なく手にしたやけに小さいジャケットの裏側。
神田は会社帰りの本屋で何気なくながめるAudio雑誌。......。
だったかもしれない。
それぞれ、どこかで読んだような説明書きだとは思ったが、思い出せなかった。
ましてや、それぞれが追い求めていたはずの「飽くなき原音追求の世界」などと。
++++++ 付録 ++++++
***レコード針の誕生 ***
第二次世界大戦後の1950年代初頭、ナガオカは初めてサファイアレコード針の開発に成功する。ただし、この当時は一般向けには納入されておらず、未だアメリカ軍や、GHQ関係者など一部の特権階級に向けた高級品でしかなかった。*(レコード針&オーディオ製品販売/YTVS AUDO のサイトより引用)
そのサファイアレコード針が一般向けに流通し始めるのは1958年(昭和33年)のことである。
***レコード針の世界ブランドへ***
1971年(昭和46年)には社名を「株式会社ナガオカ」に改め、1973年(昭和48年)になると、自社製のダイヤモンドを先端に取り付けたレコード針の製造を開始する。使用素材をこれまでのサファイアからダイヤモンドにすることで、音質の良さを最大限にまで引き出すとともに、日本のみならず世界中のオーディオファンからも高い評価を受け、「音のナガオカ」として高品位ブランドの栄誉を手にするまでになる。同時にこのころからオーディオアクセサリーの製造・販売を開始する。
ナガオカのオーディオブランドであるジュエルトーン「宝石が奏でる音階」が発足するのはこの頃の事である。
ただ、ダイヤモンド針を開発しただけではレコード針業界の頂点には届かない。 この時ナガオカは恐るべき手を打つ事になる。 業績の数十%に匹敵する額を投じて日本中のレコード店及びオーディオショップにレコード針と自社製品の陳列用にデラックスなショーケースをイージーオーダーで配布していったのである。 小規模店舗から大規模な店舗まであらゆるタイプのショーケースを配布し他社製品の駆逐と自社ブランドの独占を実行に移していった。 これが図に当たり瞬く間に先駆者である企業が倒れていき、ナガオカの敵は存在しなくなった。 このパフォーマンスは創始者である、故長岡栄太郎氏の持論である「他社は交換針を部品と考えているが、私は商品と考える」と言う言葉を具現化したといって良い。 ナガオカにおける真の絶頂期はこの後ピークを迎える事になる。
そして1984年(昭和59年)5月には、ダイヤモンドレコード針の生産数が月産100万本を達成するまでになる。
この当時のナガオカを語るエピソードが存在する。 ナガオカの営業車はスバル360から始まりパブリカ・サニー・カローラ等とステップアップしてきたわけだが、業績が頂点に達する頃、営業車を一挙にスカイラインに切り替えている。 当時ケン&メリーのキャッチフレーズで騒がれたあの車である。(ワゴンに至っては特注車である。) 乗用車タイプとワゴンととそれぞれ一挙に切り替え導入しているのである。業績の凄まじさが伺える。
同時に当時のオーディオ雑誌、FMファンやレコパル等に毎号1ページから2ページ分の公告を載せる様になり、TBSの土曜日夜8時に会社発足からの悲願であった冠スポンサーとしてマンダム・サントリー等と肩を並べてCMを全国に放映するようになる。 また、山形のFM放送権利を取得していた企業と言う事は余り知られていないが、当時は権利は持っていてもFM放送自体が企業に利益をもたらすと言う考えは無かった為、実際には放送事業そのものには着手していない。 この当時はNHK FMとFM東京の2社しか存在していなかった時代の事である。
その最中、ナガオカは世界的にも前例の無いリボン式カートリッジの開発に着手する。 リボン式とはカートリッジの内部構造を銅線では無く極薄の銅板を巻くと言う形状を持つカートリッジである。 基本技術は金箔を製造する過程における技術の応用と言われているが現在では失われた技術であり、ナガオカの関係者においてもその製造工程を完全に把握しておられる方は少ないと言われている。 完成披露は晴海で行なわれていたオーディオフェアにおいて一般公開されかなりの反響であったと言う。 ただし、生産数と販売期間はきわめて短く生産完了の背景にはあまりにも生産コストが高すぎる事等から製品化された3モデル及び試作段階の2モデルを最後に生産及び販売を終了している。 早すぎた登場が悔やまれる製品であり、主要部品にボロンをいち早く取り入れていたがこれが裏目となった。 ボロンは現在でも加工が容易とは言えない硬質金属であり当時のカートリッジにおける採用はオーディオメーカーの大半が有効である素材と知りながら加工の難しさから回避していた現実がある。 カートリッジメーカーとして名高いortofonやSHURE等も採用を見送っていたのである。 このカートリッジにおける撤退からナガオカはカートリッジにおける地位の確保に失敗し最終的にカートリッジにおける知名度を上げる事は出来なかった。これは現在もナガオカにおけるトラウマとなっている。
***レコード針の衰退、旧ナガオカの終焉とその後***
1980年代中期になると、音楽メディアがアナログレコードからCDに取って代わられるとともに、ナガオカは主力のレコード針の販売が低迷。起死回生を狙うべく、CD用アクセサリー(CDクリーニング用スプレー、CDクリーニングクロスなど)も順次発売していくようになる。またレーザーディスク(LD)部門にも参入しLD用アクセサリーも発売するも、売り上げは伸びず、この頃から、業績は不振を極めることになる。
1990年(平成2年)8月20日、ナガオカは多額の負債を抱え事実上倒産。そして、自社でのレコード針の製造を打ち切るとともに、9月、会社を解散。これと同時に、旧ナガオカの営業・販売部門を新会社の株式会社ナガオカトレーディングに、製造部門を山形ナガオカ株式会社(現・株式会社ナガオカ)、株式会社ナガオカ精密にそれぞれ分散された。
多額の負債を抱えて事実上倒産との記載があるが、正しい表現ではない。 ナガオカは赤字経営に転落する以前に企業保有の財産及び資本金等を損なう事無く解散の決議を役員会にて決定している。 役員会では存続派と解散派の間で激しい議論が戦われたが、代表取締役の判断により解散への舵を切った。 戦後から平成年間へ至る現在においても、負債を出さずに解散した極めて稀な企業であり、解散の為、役員及び全社員に全て退職金が支払われている。 但し役員保有の株式等における買戻しに関しては事実上最低限の保証に留まった。 異論もあったようであるが概ね解散に対する合意の中で取り決められたものであり資金確保の観点から株式保有役員及び関係者が譲歩した形と言える。 つまり、株主総会及び役員の総意による任意解散であり赤字の損益を回収する為の強制解散では無く、また前述にある様な倒産後の解散等と言う手続きも法的にあり得ないのである。
当時の新聞にも一面で報道されているが赤字経営による倒産や赤字と言う文字は見出せない。 経営上の業績と言う点では赤字であったと思われるが企業母体として保有する資産及び資金は赤字に至る事無く解散を迎えている。
解散に至る直前までナガオカの社内では東芝技術陣とのコラボによる新型カラオケ装置の開発やハイスピードカセットダビング機能機器の開発とカラオケの専門ショップの経営等が話し合われており、VHS型ホームビデオ試作機器の製作及び富士カセット技術陣とのコラボによるビデオテープの試作も行なわれていた。 特にハイスピードカセットダビング装置に関してはダビングによる音質劣化を殆ど感じさせない製品であったが、著作権の定義が曖昧であった為、発売時期を逸した側面も存在している。 新型カラオケ装置やハイスピードダビング機器等は既に製品化目前であり、量産化前の最終機器を横浜等のスナック等に配布し最終試験を行なっている最中であった。 ナガオカと東芝の技術陣が試験を行なっていた最終モデルは当時の8トラック型カラオケでは無くカセットテープとCDによる製品であった。 ナガオカがカラオケショップへの進出を検討していたのは未だ第一興商等が世に出る遥か以前の事である。
ナガオカでは最終段階においても業績における可能性を模索しつつ事業展開の見直しを模索していたのである。
ナガオカの解散には何段階かのステップが存在し、解散への決定を役員会にて容認した最初の作業がジュエルトーン(ナガオカのオーディオブランド)の吸収であった。
ジュエルトーンは不採算部門ではなかったが既に解散を容認した時点で資本の集中を図り社員の生活と安全を考慮すべきとの判断から独立ブランドであったジュエルトーンはナガオカ製品となりロゴだけが残され解散に至るまで使用された。
同時に豊島区の大塚に存在した本社ビルの売却先の選定及び大月に存在した工場の処遇等綿密に計画された解散処理が粛々と実行されて行った。 特に本社ビルは都内において一等地と呼べる場所に存在しその売却先選定に細心の配慮を払った。
また、現在のナガオカトレーディングが供給している一部製品にもジュエルトーンのロゴが使用されている製品が存在していた。(主にカートリッジ等。)2009年以降はナガオカのロゴになっている。