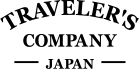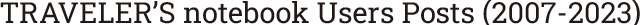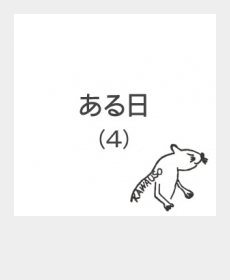
ある日(4)
その日.....、都内のアパートの一室でレコードを聴いていた青年がいた。
ターンテーブルは、昨年、晴海で開かれたAudio展でデビューしたばかりのリニヤ式と呼ばれる画期的なプレーヤーだった。彼の名前は神田といった。神田は都内の私大に通う2年生だ。高校生の頃よりAudioに懲りだし、LP・EP盤はもとより、ダンボール3箱分のオープンテープのコレクションも抱えていた。彼の部屋を訪ねる友人はまず、スチールのラックにドーンと縦置きにされたオープンデッキに圧倒されたものだった。そして次にYAMAHAの3WAY、もちろん左右対象型スピーカー、次にSANSUIのアンプ、トリオのチューナー・TEACのカセットデッキと、順番に目を見張った。レコードのコレクションもちょっとしたもので、1年程前このアパートに越してきたとき、すでにみかん箱に11箱というボリュームのコレクションを誇っていた。それから丸1年、バイト代も親からの仕送りもほとんどを注ぎ込んでコレクションを増やしていた。
学生街のレコード屋では一番のお得意だった。初老のマスターは「神田さん」「神田さん」と常に愛想がよかった。なにしろ、月に5・6枚はコンスタントにアルバムを買っていたもんだった。それをいいことに神田は授業が終わると一度アパートに戻り、アンプ、カセットデッキの電源を入れ、ターンテーブルのダストカバーも開け、そのレコード屋に出掛ける。決めていた2枚を求めすぐアパートに戻り、内1枚をカセットデッキで録音し、ふたたびレコード屋に戻すのだ。
「ああ~ん、やっぱりこっちは持ってたよ」
そんなサクセスストーリーを友人に自慢してみせる憎めないやつだ。
きょうは部屋を訪ねる友人もなく、いつになく上機嫌で旅行カバンに荷物を入れながら、最新のリニア式プレーヤーでお気に入りのEAGLESをかけている。夏休みに入った神田はきょう帰省するのだ。
--------------------
***リニア式プレーヤー***
ターンテーブルの脇に固定されたトーンアームでレコード面をトレースする従来の方式に対し、トーンアーム自体を横に移動させて、常にレコードの溝に垂直に針が当たるようにしたプレーヤーを言う。この原理により、レコード針のトレース条件が常に一定になり、遠心力を緩和するインサイドフォースキャンセラー、トーンアームが次第に中心に偏ることによる仰力を緩和するラテラルバランサーなどの機能を不要としたシステムである。
外周と内周の歪みの差:
レコードはテープやCDと異なり盤の外周に対し内周で歪みが増えるという特有の欠点がある。正しく調整されたリニアトラッキング・プレイヤーを用いれば問題は無いが、ピックアップ部が弧を描いて動作する通常のトーンアームではインサイドフォースやオーバーハングずれの影響を解消する事は容易ではない。
外周と内周の帯域差:
レコードは角速度(回転数)が一定であり、内側に行くほど線速度が遅くなっていく。そのため、内側に録音された音ほど高周波特性が悪く(帯域が狭く)なっていくという特徴がある。
音楽が販売される媒体として、レコードは長い間、非常にポピュラーであった。このため、レコードがCDにとって代わられた現在でも、音楽を録音したものを制作、販売する会社は「レコード会社」と呼ばれる。CDなどを販売する小売店が「レコード店」と呼ばれることも多い。
・フランス人はレコードの発明者を自国のシャルル・クロであるとしており、彼の名を記念したACCディスク大賞がある (ACC: Academy de Charles Cros)。
・元々レコード盤には帯電防止剤が添加されているが、かつては盤の材料に帯電防止剤を大量に添加するEMIミュージック・ジャパンのようなメーカーも存在していた。これを「エバー・クリーン・レコード」と称し、その証として赤い半透明の盤にしていた。しかし経年劣化によりこの添加物が化学変化を起こすためか、久し振りに聴いたら音が歪んでいたという指摘もなされている。
・可変ピッチ記録のLPレコードは溝の疎密から音の大小が推定できるため、慣れると長い曲の聴きたいところを簡単に頭出しすることもできた。
・レコード盤の溝は一般には音質の良い外側から刻まれるのに対し、反対の内側から録音再生していく方式を採っていた用途もあり、円盤式トーキーのためのレコードや、テープレコーダの普及以前に放送局などで広く用いられた円盤録音機に多く見られる。なお、通常のレコード盤の変わり種としても、実際にジョークのレコードとして販売された例がある。逆に、後のコンパクトディスクにおいては、ディスクの内側から再生する方式が標準とされることになる。
・落語家の初代桂春団治が、日東レコードの協力のもと、本物の煎餅でレコードを作った事がある。煎餅が湿気ない様に缶にパッケージされていた。これは1926年のことで、天理教大祭の人出の多さを当て込んだものだったが、値段が高かったため全く売れず、春団治は大損した。なお、煎餅レコードは落語やコントなどが収録され、「聴き飽きたら食べる」というコンセプトのものであった。
***カートリッジ***
レコード表面の音溝の振幅を、電気信号に変換する装置である。音溝をトレースする「針先(スタイラスチップ)」と、これを支える「カンチレバー」、カンチレバー後端に置かれる発電コイル、信号出力用の接点(ピン)で構成される。なお、ステレオの場合は、出力ピンが4本 (L+/L-/R+/R-)、モノラルの場合は2本 (+/-) になる。
スタイラスチップ(針先)は、ダイアモンド、ルビー、サファイアなどの硬度の高い物質で作られており、断面の形状は、円形、楕円形、ラインコンタクト等がある。特にラインコンタクトは1954年フランスのレコード・メーカーパテ・マルコーニ(Pathé-Marconi:現在のフランスEMI)で考案された「深さ方向に大きい曲率と、小さな実効針先曲率で音溝に接触させて諸特性を改善する。」といった提案思想が、柴田憲男の4チャンネル針で初めて実現化され、チャンネル・セパレーションや周波数特性で大幅な性能向上、およびスタイラスの長寿命化を実現した。
スタイラスチップの寿命については、判定の基準として「曲率の変化、変化比を基準とする。再生歪みを基準とする。磨耗面の幅を基準とする。」方法が考えられるが、針先の形状や使用状況によって磨耗の状況が異なってくることから一概に「寿命は何時間程度」と定義するのは難しい。レコード盤面に接触するため機械的な摩耗や摩擦熱などにより消耗・摩滅する。消耗が進んだ針の使用はレコード盤を傷める原因となるため、一定時間おきでの交換が推奨される。
カンチレバーは、先端にスタイラスチップを装着した細長い棒で、スタイラスチップと反対側に発電機構を備える。スタイラスチップをレコード音溝に押し付ける機能と、音溝の振幅に正確に追従し電気信号に変換する2つの機能を持つ重要な部品である。カンチレバーの形状には、無垢棒、アングル、パイプ、テーパー形状などがある[2]。カンチレバーのおもな材料は安価で加工が容易なアルミニュウムやジュラルミンなどの軽合金が用いられるが、高級品には高度な加工技術を必要とするが音響特性に優れたボロンやベリリウムが用いられる。
発電方式によって、MM (Moving Magnet) 型とMC (Moving Coil) 型に大きく分けられる。
MM型:
カートリッジ内部に差し込まれたカンチレバー後端部分に永久磁石を取り付け、この永久磁石の振動によりその周囲に置かれたコイルに発生する起電力を再生出力とする方式。
MC型 :
カートリッジ内部に差し込まれたカンチレバー後端部分にコイルを取り付け、その周囲に永久磁石を置く。このコイルの振動によりコイルに発生する起電力を再生出力とする方式。
両者では、構造が簡単なMM型はパワフル、振動部分の質量を小さくできるMC型は繊細で高音質とされる(製品によって傾向は異なる)。しかしMC型は構造上コイルを大きくすることができないため出力電圧が小さく、イコライザアンプ(後述)の前段に低雑音の前段増幅器(ヘッドアンプ)または昇圧トランスを必要とする。また、スタイラスチップが磨耗した場合に、構造上MM型がスタイラスチップとカンチレバーを含めた「レコード針」のみの交換であるものが多い(一部高級品に全体交換のものもあり)のに対し、MC型はカートリッジ全体の交換となるため、交換時の費用はMC型のほうが大きくなる。このように、コスト的にはMMに分があることもあり、一般用の製品は殆どMM型である。
--------------------
鼻歌交じりの神田は次第に旅支度に専念し始める。電車の時間が気になりだしたからだ。田舎の岩国までは6時間、東京駅の書店でAudioジャーナル誌と缶ビールを買う時間もある。ボストンバックを片手に慌ててアパートを飛び出したとき、すでに景気付けにかけていたレコードのことなど忘れていた。
ふたたび神田が戻ったのは40日後のことである。出掛けたときのボストンバックを片手にドアを開けた神田を熱気が包んだ。そして、40日間分の熱を溜め込んだ部屋からは妙な音が聞こえてきた。
神田は「シー、シー、シー」と聞こえるかすかな連続音を探した。
音源はすぐ見付かった。自慢のリニア式プレーヤーからなのだ。レコードは回転していた。あの日からずっと人知れずレコード針は回転するレコード面をトレースし続けていたものらしい。
「シー、シー、シー」
ターンテーブルをのぞきこんだ神田は唖然として立ち尽くした。ターンテーブルは確実に回転していて、レコード針はアルバムの最後の溝の円周をなぞり続け、溝の両サイドにうっすら切り粉の山を築いていた。恐る恐るトーンアームを上げてみると針はすでにレコードを貫通していて、ラバーマットに円を描いていることがわかった。
神田は特大のドーナツ盤を眺めながら寒気を感じていた。それはダイヤの鋭さもさることながら、引っかき傷を音源とするレコードという回転系自体から生まれる強いアナログ性なのだ。
「ほらっ、これさ~っ。かなりのものだろ。40日間さ」
「ものすごいエネルギーを感じるだろ?」
神田は久々に顔を会わせるアパート仲間の中で自慢なのだ。
「なんだって、神田さん?、レコード掛けっぱなしで田舎に帰っちゃったんですか?アハハッ」
そんな噂を聞きつけてヒョッコリ顔を出したのは同じアパートの後輩、米山だ。
「『アハハッ』じゃないよ、米山。ほ~ら、これが、夏休みの工作だ。巨大ドーナツ盤。製作者はダイヤ針だがな」
「はあ、本当にこれはダイヤモンドカッティングですね」
巨大なドーナツと中味を両手に米山はそう言った。
「機械っていうのは恐ろしいよな.....
ところでお前、今度Audioの展示会いかないか?」
神田はそう言うと米山に、開いていた雑誌を渡した。
. . . . . . .
今回の新製品の試聴会は○月○日、千駄ヶ谷のオンキョウスタジオで開かれた。
今回の審査員は長岡鉄男氏はじめ、赤井、早川両氏、本誌松下というメンバーで試聴室に入った。装置はすでに1時間ほど前からあたためられていて、メーカー担当者から簡単なシステム説明の後、穏やかな雰囲気の中始められた。
以下、各氏のコメントを紹介する。
「今回のシステムにはかなりの期待を抱いて試聴室に入った。先ず、出だしの音を聴いて音声解像度が格段にアップされている実感があった。音にメリハリがある。多分、これを聴いてM社のRBー120に近いイメージを持たれる方も多いと予想されるが、むしろ昨年V社から発売されたKシリーズにJ社のイコライザーをミュートさせた音に近いかも知れない。それを単品で再生してしまう辺りにこのシステムの真価がある」
(長岡氏)
「流石、独自の発想を持つS社だと脱帽させられた。高域の伸び具合、中域のしなやかな表情といい申し分ない。しかしひとつ難点を言わせてもらえば、超低域帯において若干音がこもる傾向があるように思われるが、通常の再生装置では聴き取れるかどうかの方が問題であろう」
(赤井氏)
「神田さん、今度はこのシステム買うんですか?」
「バカ言え、こいつは業務用のやつさ。50~60万は下らないやつさ。とてもオレらになんか手が出ないけど見るだけなら出来ると思ってさ。
オレはつくづく思うよ。こういう本の講釈に弱いんだ。どうしても目にしてみたくなってしまうんだ。レコードなんかもともと単なる引っ掻き傷が音源なんだから、どう料理しても限界は見えているはずなのに、よくも次々と理屈を思い付くものだと思ってさ。
知ってるか?、そもそもレコード自体完成された音源再生システムじゃない。LP盤の中心近くの曲は音質が悪くなるという理論。盤の外周近くの針にかかるスピードと、盤の内側よりではトレースする速度が変わってしまう。いつも何気なく聴いてしまうが、あれ、録音したときのカッティングマシーンも同じように外側から内側に吹き込んでいるから気がつかないだけで、陸上のトラックと同じで、外側の方が速く走らないと追いつかないわけさ。まあ、ものすごく細長い短冊のようなレコードじゃ聴くのも大変だろうがな。音源があいまいなんだから、あとはなんとでも講釈はつけられるってことさ。その記事だって
『地球では上り坂が続けば、やがて下り坂となるでしょう。なぜならば地球は球体ですから』
なんて言ってるのも同じさ。オレだってなんとでも講釈できるさ。
米山、だからこそ、オレは大学卒業したらオーディオメーカーに入りたいんだ。絶対というものがないから様々なことが試される。これが原音追求の世界さ。オレはそこに無限の可能性を感じるんだ。....