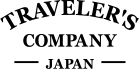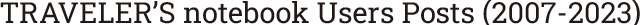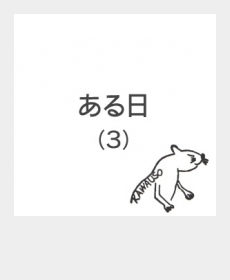
ある日(3)
■LPレコード
アメリカ人ピーター・ゴールドマーク (Peter Goldmark) が開発、1948年6月21日にコロムビア社から最初に発売された。直径12インチ (30cm) で収録時間30分。それ以前のレコード同等のサイズで格段に長時間再生できるので、LP (long play) と呼ばれ、在来レコードより音溝(グルーヴ)が細いことから、マイクログルーヴ (microgroove) とも呼ばれた。また、回転数から33回転盤とも呼ばれる。これ以降、従来のシェラック製78回転盤は(主に日本で)SP (standard play) と呼ばれるようになった。
■EPレコード
LPと同じ材質・音溝で、RCAビクター社が1949年に発売した。直径17cmで収録時間5分。EPはextended playの略。回転数から45回転盤とも言う。オートチェンジャーで1曲ずつ連続演奏する用途が想定された。オートチェンジャー対応を容易とするため保持部となる中心穴の径が大きく、ドーナツを想起させるため、ドーナツ盤とも呼ばれた。
■LPとEPの共存
LPとEPは初期の一時こそ競合関係にあったが、長時間連続再生可能でクラシック音楽の全曲収録や短い曲の多数収録が可能なLPと、SP盤並の収録力(片面あたりポピュラー音楽1曲程度)のままでディスク小型化とオートチェンジャー適合化を指向したEPは、実用上の性格の相違から棲み分けが容易で、基礎技術自体はほとんど同一のためレコード針も共用できたことから、ほどなく双方の陣営が相手方の規格も発売し、双方がスタンダードとなるという形で決着がついた。
***ドーナツ盤***
その名のとおり盤の中心が大きく丸く抜かれたレコードである。ちなみにA面1曲・B面1曲だけのソースとなる。そして、スペーサーと呼ばれるプラスチック部品が不可欠なレコードをそう呼んだ。ただし、音質は通常のLPでの内周部にあたるために劣ると言われていた。
■初期の円盤式レコードは、収録時間が直径10インチ (25cm) で3分、12インチ (30cm) で5分と、サイズの割には短かったために、作品の規模の大きいクラシック音楽などでは、1曲でも多くの枚数が必要となり、レコード再生の途中で幾度となくレコードを掛け替えねばならなかった。
■特にオペラなどの全曲盤では、数十枚組にもなるものまであり、大きな組み物はほとんどの場合、文字通りの分厚いアルバム状ケースに収納されていた。今でもディスクのことを「アルバム」と呼ぶことがあるのは、それに由来している。
■また、ポピュラー曲に関しては、面ごとに違う演奏家によるレコードを複数枚集めたアルバムが作られる場合もあり、これを乗合馬車(ラテン語でomnibus)に見立てて、「オムニバス」と呼ぶようになった。現在「コンピレーション・アルバム」と言われるものがかつては「オムニバス・アルバム」と言われたのはこれが由来である。
・1960年代後半までは複数のレコードを連続演奏することが可能な機種も存在した(オートチェンジャー)。業務用のジュークボックスにおいてはアームによりレコードを交換する機構が用いられ、一般家庭向けの製品では特殊な長いスピンドルを装着してレコードを宙に浮かせるように重ね合わせ、演奏が終了するごとに1枚ずつターンテーブル上に落下させる機構が用いられた。
LPレコードとEPレコードについて 追記
当時、LPレコードの最長録音時間はベートーベンの第9交響曲(両面使用)とEPレコードについてはビートルズのヘイ・ジュードが最大基準と、オーディオファンの常識とされていたが、真偽の程は怪しかった。
先述のスペーサー。
たまたまその部品が見つからない時、誰もが1度や2度チャレンジした経験というものがあった。それは微にも例外ではなかった。
彼はEP盤の両サイドを4本の指でつかむところから始めるべきだと考えた。
「左右同じ力で出来るだけ軽く持つようにしよう」......
親指の股を一杯に開いて、親指と中指の先端で持つ。まったく左右対象の手の形。
レコードは今、4本の指先に均等に触れている。しかも四つの支点は円周を正確に4分割していて、一段と精度がアップした気分にさせてくれる。そして、ゆっくり回転面に近づける。
出来るだけ回転面に近く......
触れそうで触れていない......。
顔を真上に持っていって、両目を交互に瞬きながら、ターンテーブルのヘソとドーナツ穴の寄りとを見比べる。もう寸分の狂いもない。ドーナツ盤の真っ芯に正しくヘソは回転を示し、すべての準備はとどこおりなく整った。あとは4点同時のリリースだけ。微は全神経を4本の指先に集め、一瞬にすべてを賭ける。
呼吸を整え元気よく。
大胆かつ慎重に。
「ヘタリ」
盤はラバーマットに着地し、ほぼ真円を描いて回転している。等速円運動。これがまさに科学の教科書にあったその運動。生活に身近なところでは扇風機の羽根とこれくらいしか見当たらない。
針を落としてみよう。真円の正確さは、すぐ音声となって表れる。
「プチッ、プツリ、プツリ......」
いよいよイントロが...、少しラリっている。刻みギターが、ベースが確かにラリっている。
まだ少しずれている。
「私は今、まやかしの正確さに甘えながら聴いている」
微は次第にそう思い出す。
「いまこそ勇気を持って微調整を加えるべきである」
「きっぱりトーンアームを持ち上げ、膨らんだ楕円を指先で真円に戻すんだ」
「指先は人差し指がいいだろう。楕円が一番広がった円周の頂点を中心に対して垂直に押そう」
楕円の頂点を見極めながら1分間に45回転を体に植え付ける。
「今、..はいっ、今、..はいっ、今、いった」
チャンスは1.33秒に1度。
「はいっ、」
人差し指がわずかに左に流されて、レコードも時計回りだったと言っている。そして、さらに少し大きくなってしまった楕円を見るのである。
「はいっ、」「はいっ、」「はいっ、」
なおも修正を繰り返す。やることすべてが裏目に出る世界がここにある。
そして、とうとう「カム」と呼ぶにふさわしい荒れ狂いようになって手も付けられない。微はとっくにEP盤をあきらめたかわりに、無理やりその楕円に針を落としてみたくなる。
「プチッ」
すると一瞬トーンアームは急速に中心へ吸い寄せられ、そこから一気に外側へ無限大に拡散して、盤から弾き飛ばされてしまう。
『ズズズズズ.....』
黒いラバー面に弾き飛ばされたレコード針が、それでもなんとか音楽にしてやろうと溝を探す音なのだ。そして、誰もがドーナツの穴の大きさをかみしめ、スペーサーと呼ばれる単純なプラスチック部品の偉大さを思い知らされることになる。
『ズズズズズ、.....』
針は測定しきれない大きな力で振り切られた地震計のようにゴムマットに丸い直線を描き、大回転の前に無力な我々は、直線になってしまった自身の心電図を眺めているような気持ちのまま「ゴムバンド」のスマッシュヒットを黙って聴くだけである。.....
「そんな時代もあった」.....
微は次々取替えていたアルバムの手を休め、しばらく回転するレコード面に眺め入った。
カートリッジからレコード面へ斜めに突き出た針は、まるで止まっているように揺れていない。
ナイトクルージング。波のない入り江をクルーザーで進んでいる。
電気を消した部屋の中で月明かりに黒いエボナイトの丸い平面が、まるで油でも溶かしたようにヌメヌメ輝いて見えていた。
幸せな微は微笑んだ。
***コンパクト盤***
回転数33 1/3r.p.m.
直径17cm(7インチ)
EP盤の回転数を45から33 1/3に落として片面に2曲 - 3曲ほど収録したものをこう呼ぶ。70年代など、LPが高価だった時代に、曲数が多く安価だったことで学生たちに好評であった。