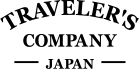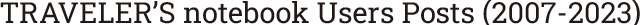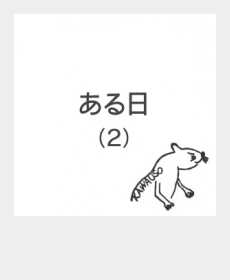
ある日(2)
ある日......、誰もが意外な光景を眼にしていた。
それは新聞のラジオ欄であったり、FM雑誌の番組欄であったり、また、実際の番組のDJのあいさつであったりした。
日曜の昼下がり、人気DJの小林克己はこう言った。
「さて、皆さんにお知らせがあります。長い間皆さんに可愛がっていただいてきましたこのナマオカ・ミュージック・インハイホニックですが、今回を最後に終了することとなりました。今まで様々なリクエスト、お便りいただいたリスナーの方々、また多くのミュージックファンの皆さん、改めて感謝します。
番組は終わっても、いい音楽はいつまでも皆さんの心に生き続けることでしょう。製作者を代表してお礼申し上げます。
なお、先週までのリスナープレゼント、高級ベルベットを使用したナマオカ・レコードクリーナーケミックと、針先を楕円にカットし接着面積を飛躍的に向上させたナマオカ・オーバル針の受付は有効です。プレゼントは発送をもって発表と代えさせていただきますので、もうしばらくお待ちください。
さて、時間がまいりました。
スィーユウアゲイン、ネクストチャンス。チェケラッ!」
もちろん、新聞のラジオ欄やレコパル誌の番組欄に印字された『最終回』という文字に気付かなかった人物や、番組の最後を待たずにラジオを切った人物には、いつもと変わらぬ日曜日だった。
「なんだ、番組終わっちゃうのか?...」
微はそうつぶやきながらターンテーブル
にレコードを乗せた。レコードはお気に入りのDoobie brothers。ターンテーブルはようやく先週完成したばかりのLUXKITバキュームディスクなのだ。
バキュームディスク***
アルミダイキャストのターンテーブルの上に特殊なラバーシートを敷き、ラバー面に開けられた吸気孔からレコード盤とシート面の間の空気を吸引する。するとアルミダイキャストとレコード面は一体化し、ターンテーブルと同じ質量を持つレコード盤が生まれる。ひずみ、歪みのないフラットなレコード面と重質量を備えた回転面はより原音に近いひき締ったソースを引き出すことを可能にした。***
微はAudio雑誌にあったこのうたい文句に目を輝かせたのだ。彼は飽くなき原音追求の魅力にとりつかれた多くの純粋なAudioファンの一人なのだ。
思えば3ヶ月ほど前、夏のボーナスを頼りに自身の何がしかの技量に賭けて購入したキットだ。それがようやく幾晩もの寝不足の夜を越えて、先週完成したのだ。
微は嬉しかった。
スイッチを入れるとレコードがピシュとターンテーブルに吸い付き、ズッシリした正確な回転を示すのだ。もちろん、モーター制御はクォーツロック。水晶発振による回転数に遅進の狂いはない。しかも、そのモーター自体がダイレクトドライブ。ターンテーブルの脇にセットされたモーターからベルトで駆動させる従来のベルトドライブ式と違い、モーター軸そのものがレコードを置く中心そのもの。そのモーターもPIONEER社製と明記されていて、これ以上の正確さもないだろう。2・3年おきにベルトを交換する手間も要らず、曲の長短もなく、何年聴いても歌詞カードにかかれた演奏時間ジャストで再生され続けるのだ。そして、設計図をにらみながら、基盤に取り付けた幾つものダイオード、コンデンサー、そこからハンダ付けで取り出し、別の基盤へと渡らせた細い電線一本一本が正しかった。
そもそもそれは、
「よしっ、自分の力で作ってやろう!」
自身が信じた考え方が正しかった証明として、今、規則正しい回転を示しているのだ。
微は次々お気に入りのナンバーに針を落とした。
「Long train running」
2曲飛ばして
「China grove」
面を返して
「Natural things」
盤を替えて
「Doobie street」
また盤を替えて
「Minit by minit」
へと......。彼はベスト盤のカセットを作るのに忙しいのだった。
微はもともとEP盤ファンだった。
中学生の頃、ラジオの深夜放送を聴くことが流行った時代があった。クラスの話題といえば昨夜の深夜放送のこと。リクエスト葉書が読み上げられた学級委員の女の子など、一気に生徒会長候補にまで押上げてしまうほどの波及効果を持ったブームだった。
彼女は微に1枚のEP盤を貸してくれた。
「She loves you」
ビートルズというイギリスの4人組みのスマッシュヒットだった。歌謡曲や演歌しか耳にしたことのない微にとってアップテンポなビートの効いた一曲は、おしゃれで新鮮だった。彼の覚えている限り 「10人のインディアン」・「ロンドン橋落ちた」 以来の英語の歌だったりもした。
番組の中心は、当時「洋楽」とジャンル分けされたポップスと呼ばれたミュージックだった。
ホリーズの「ごめんねスザンヌ」。
エジソン・ライトハウスの「恋の炎」。
「二人のシーズン」はゾンビーズ。
「西暦2525年」ゼイガーとエバンス。
マッシュ・マッカーンの「霧の中の二
人」......。
すべて曲名は日本語、歌詞は英語というのが少し不思議だった。果たして、やつらが何て歌っているかのヒントは曲名の短い日本語がすべてだった。結果、メロディに合わせてどのようにでもイメージは膨らんでみせるのだった。
小遣いが出ると町のレコード屋に通った。
洋楽と書かれた棚の前でヒットチャート№1のブランドものにするか、自分の直感を信じてチャートの5位、6位のものに甘んじていいものか、迷い切るには時間が足らなかった。
「EP盤っていうのは、アルバム(LP盤)のサンプルなのさ。......
そのアルバムの一番良い曲がA面、最低ラインがB面さ。だからみんなB面なんか聴かないから無駄なのさ」
当時、ポップス通と呼ばれていた友人はそう言ってEP盤を決め付けていた。なるほど、微の何枚かも傷だらけでうっすら白くなったA面に対して、新品同様に黒光りしているB面ばかりだった。でも微はそいつが嫌いで、EP盤が好きだった。回転数も『33・1/3』に比べ、『45』と切れもいい。学校のカバンにもすっぽり納まり、持ち運ぶにも便利。LP盤のように溝の切れ目を探すこともなく、スマッシュヒットの世界にダイレクト。余計な事を言わず、スマッシュヒットだけを伝えて去って行った。それはそのままアルバムを「通し」で聴くこともなく、スマッシュヒットだけで満足してしまう薄い微のミュージックライフでもあった。