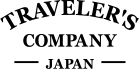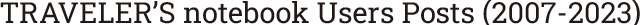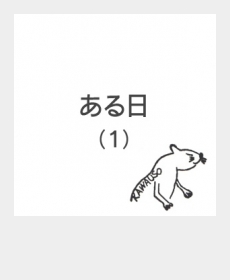
ある日(1)
レコード取扱いのご注意
1)レコードをジャケットから取り出すときはまず手を洗ってからにしましょう。
2)レコード盤はエボナイト樹脂でできていますので、盤面に手の油や指紋、ホコ
リ等、付着しないように注意が必要です。
3)そのまま放置しますと音質低下、針飛びの原因になります。汚れがひどい場合
にはレコードクリーナーケミックで盤の円周に沿って拭きましょう。別売りの
クリーナースプレーを併用すると効果的です。
※レコードは1年に一度程度水洗いし、陰干しすることも効果的です。その際、
バケツなどにレーベル面が塗れぬように漬け、録音溝だけを洗うよう注意します。
4)ジャケットからは静かに引き出しましょう。盤のエッジを持つようにして、プレ
ーヤーのターンテーブルの中心にセットします。
5)EP盤のレコードを聴くためにスペーサーというプレーヤーの付属部品が必要で
す。無くした場合はレコード店、楽器店音響製品取扱い店で購入できます。
6)ターンテーブルの回転数を確認します。LP盤の場合は33.1/3、EP盤で
は45回転へ速度選択レバーを合わせます。いずれも1分間の回転数です。プレ
ーヤーの機種によってはストロボというピボットがターンテーブルに刻まれてい
て目視できるものもありますが、1ヶ月に一度程度、回転数のチェックが必要で
す。また、回転数の遅れがいちぢるしくなった場合には、ベルトドライブの交換
が必要です。ベルトの購入はプレーヤーの製造メーカー、販売店にお尋ねください。
7)盤面の回転状態を確認します。注意するのは盤面の上下の歪みはないか(LP盤)
ターンテーブルの中心とレコード盤との円周のふらつきがないか、スペーサーが
正しくセットされているか(EP盤)等です。
8)トーンアームを上げレコード針を確認します。ホコリ等が付着していないか、針
先が曲がっていないか等です。針先の汚れがいちぢるしい場合には専用のクリー
ニング液も市販されていますが、針の寿命とも考えられます。針の寿命は概ね、
サファイヤ針で100時間、ダイヤモンド針で500時間といわれています。そ
のまま継続して使用しますとレコード盤の溝に傷がつく原因ともなりますので定
期的な交換をお勧めします。替え針もレコード店、楽器店、音響製品取扱い店で
購入できます。
9)レコード盤面へ針を乗せるときは、衝撃の起こらないよう注意が必要です。また
針はできるだけ垂直に上げ下げするよう心掛けましょう。横にずらしますと、レ
コード盤の溝に傷がついて針飛びの原因となります。
10)レコード盤を聴き終わったらターンテーブルに放置せず、ジャケットに戻し保
管するように心掛けましょう。保管の際には平置きや重ね置きはさけ、縦置きし
ます。また、高温多湿の場所は盤の歪み、カビの原因となりますので注意しまし
ょう。
引越し等のご注意
供給電力の違いにより中部以西60HZ、中部以東50HZと別けられています。
(図参照)このためそれぞれの圏外へ移った際には、プレーヤーのモーターの回
転が変化します。微調整つまみのある機種は再調整しますが、調整しきれない遅
進や調整機能がない機種は、モーター交換や改造等が必要となりますので製造メ
ーカー、販売店にご相談ください。
ある日...。
会議室はいつものように議題を消化し、解散しようとしていた。
「ほかに何かご質問等ございますか?」
そこで恐る恐る手を上げた人物がいた。技術開発課長の野口だ。
「あのう、今朝の新聞にあった記事ですが、『非接触型の音声再生装置』という見出しだったんですが、光ディスクにデジタル信号化して記憶させレーザー装置で読み取る技術だそうです」
それだけ言うと野口は黙ってしまった。
「で?」
先を言うように、司会役の販売部長が促した。
「で、従来のアナログ信号を、デジタル化して再生するわけです」
野口は3年ほど前、K大の工学部から採用した二人目の社員だった。なんでも工学部卒業後、音響工学の博士課程に進み、修士終了後さも当然と入社したのだが、頭が切れるのはいいが、商売にはまったくうとい。実戦で世の中を渡ってきた者からすると実にじれったい存在にあった。
「野口君、だからそれが我が社の売上にどうつながるんだね?。何か新規事業のネタかね?」
そう言われて初めて野口は気付いた。きょうは販促会議。販売促進に直接つながらない話題は余計に敬遠される。
「お集まりの皆さんは全員忙しいんだ。わかりやすく説明したまえ」
野口はここはサラリと流して、来月の技術連絡会まで延ばそうと、できるだけストレートな言葉を捜してみた。
「要するに『針の要らないレコード』ということです」
「『針の要らないレコード』ね?。そりゃまたゲテものだね。はははっ、大体、針もないんじゃ気が入らんだろう。『蜂のムサシ』じゃないが針があるから蜂なんで、針もなきゃ蟻だろう」
と、専務は笑った。そして、こう続けた。
「野口君、どこかのスポーツ紙の記事かい?。実際そんな文句を過去に聞いたこともあった。ご存知かな?、今のカセットテープさ。
あの時はレコード会社も画期的だと、かなり乗り気でミュージックテープに流れたが、結局ある程度で落ち着いた。むしろ、レコードをカセットテープに録音して聴く需要が広がった分と、又貸し録音の減でトントンくらいかだ。まあ、うちにとっては又貸しだろうが、今流行りのレンタルだろうが、レコード盤に針さえ落としてくれればいいわけだがな。
その時思ったね、レコードというミュージックソースは文化なんだ。SP盤問題もある。レコード発祥当時より80年余りという長い流れであり、残してきた盤数ときたら把握しようもない程で、やはり我々にとっては音楽がある以上消えないレコード文化だと思ったよ」
野口と同席していた技術開発部長が手を上げた。
「専務、あながち野口君の情報も無視は出来ないでしょう。確かに実用の域には達していませんが、一応検討の余地はあるかもしれません」
あとを販売部長が受け継いだ。
「その辺りについては技術開発部長、あんたの仕事として、
野口君、我々は君が生まれる前から、針の一本血の1滴でモノラルの時代からここまでやってきたんだ。ただの鉄針からサファイヤ針、ダイヤ針、ソノシートなんて薄いレコードにも泣かされながらな、そしてオーバル針へと、その都度、世の中の流れに合わせながら乗り切ってきたんだ。それよりもなによりも専務の言われるようにレコードとは文化なんだよ。これは逆にどうあがいてもかえられない、大衆の要求なんだ。君もレコード針メーカーにいる以上、そこのところをもう少し勉強してみなさい!」
会議は持論の正当性に酔った顔付きの経営陣と、退屈な時間にうんざりした出席者の顔だけを残して終了した。